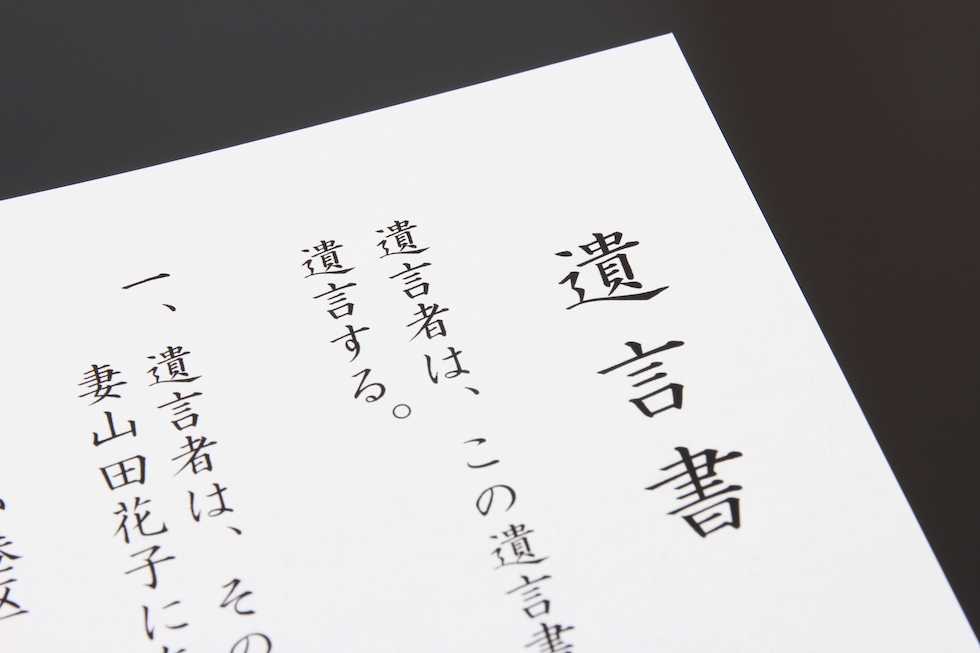
障害者の親なきあと問題についてのご相談・対策の中で、ほぼ確実に必要となってくるのは「遺言」の作成です。
遺言の種類は大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の二つに分かれます。
「秘密証書遺言」という種類のものもあるのですが、実務上ほとんど使われないのでここでは割愛します。
ちなみに障害者の親なきあと問題では公正証書遺言と自筆証書遺言それぞれの使い分けも必要になってきます。
- 自筆証書遺言とは手書き・自書で作成する遺言のこと
- 公正証書遺言とは公証役場で作成する遺言のこと
自筆証書遺言と公正証書遺言の詳細な違いにと使い分けについては、後述します。
まずは、なぜ障害者の親なきあと問題において遺言が必要なのかについてご説明します。
遺言がなかったら、どうなるのか?
そもそも遺言はなんのために作成するのか?
- 自分の思い通りに財産を遺すことで、自分の想いを実現させるため
- 相続人同士が揉めないため
- 手続きを簡略化させるため
などの理由が一般的には考えられますが、特に親なきあと問題においては
判断能力が不十分な子がいたときに遺産分割協議がストップしてしまう可能性があることを注意する必要があります。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは亡くなった方(被相続人)が遺言を遺していなかった場合、その財産をどのように分けるかを遺された家族(相続人)が決めることを言います。
遺言がない場合はこの遺産分割協議によって財産を取得する者を決めます。
しかしこの遺産分割協議には要件があります。
- 相続人全員が参加していることと
- 相続人全員が十分な判断能力を有していること
遺産分割協議を成立させるにはこの二つの要件を満たしている必要があります。
とくにこのうち②の要件について、親なきあと問題において注意点になり得ます。
なぜなら遺産分割協議に参加する相続人の中に、知的障害・精神障害があって十分な判断能力を有していない方がいる場合、遺産分割協議が成立しない可能性があるからです。
また遺産分割協議の成立を証した「遺産分割協議書」には相続人全員が役所において登録をしている実印を押印し、かつ印鑑証明書を添付しなければならないので、役所においてそういった手続きができなければ、実際に手続きなどで使うことはできません。

遺産分割協議ができないとどうなるのか?
財産の凍結について
基本的に、銀行等に亡くなった方の名義がある場合、その口座はキャッシュカード等で引き出すことができなくなります。これをいわゆる口座凍結と言います。
亡くなった方の名義の口座ひとつで生活費などを管理していた場合で、生命保険などを利用していなかった場合は、亡くなって間もなくの生活費や葬儀費用を捻出することができないこともあり得ます。(借金をせざるを得ないこともあります)
不動産の名義変更・売却の手続きも同様で、遺産分割協議を成立させ、遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければ、亡くなった方の不動産を売却することができません。
成年後見制度の利用
この時、相続人の中に判断能力が不十分な方がいることで、遺産分割協議が成立しないというような場合は、「成年後見制度」を利用する必要があります。判断能力が不十分な方の代わりに遺産分割協議をしてくれる成年後見人の選任を裁判所に申し立てます。
ただし、
- 成年後見人は一度利用するとそこから解任することが難しいこと
- 家族の意思ではなく裁判所が選んだ専門家が後見人になることがあること
- 専門家が後見人に選任された場合、月額の後見人報酬がかかってしまうこと
- 成年後見人による横領事件なども後を絶たないこと
などの理由から、できる限り成年後見制度を使いたくないという声も耳にします。
遺言による対策
しかし、生前に財産を持っている方が対策をしておけば、遺産分割協議が成立しない事態や成年後見制度を不本意に使わなくてはならないという事態に備えることができます。
その対策として最も簡単な手段が「遺言書の作成」です。
適切な遺言を作成すれば、遺産分割協議を省略することができます。
これに関しては自身が手書きで作成する「自筆証書遺言」についても
公証役場で作成する「公正証書遺言」についても同じことが言えます。
ただし、遺言の内容次第では、結局遺産分割協議が必要になってしまう場合があります。
自筆で作成する場合でも、専門家に相談して作成すべきでしょう。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらにすれば良いのかという問題についてです。ほとんどの専門家は「相続対策をするのであれば公正証書遺言にしておいた方が良い」という意見を持っているようです。しかし、この「障害者の親なきあと問題」については、必ずしも公正証書遺言で作成した方が良いとは限りません。自筆証書遺言と公正証書遺言のそれぞれの違いについてまとめます。
まず遺言をつかってできることは以下のとおりです。
1.遺言者の想いの実現
自身の財産を死後どのようにしてほしいか。これが遺言の本質的機能であり、遺言者の想いに忠実につくることが遺言の最も重要な点です。後述にある相続人同士争ってほしくないということや、死後の相続手続きで苦労してほしくないということ②~④の機能も、ある意味ではこの「遺言者の想いの実現」に含まれているとも言えるでしょう。
2.相続人の紛争予防
遺言と聞くと、やはり遺産相続争いの予防を思い浮かべる方は多いかと思います。実際に遺言を作成する方の多くは、相続人間の不仲を心配して遺言書の作成に踏み出す、傾向にあります。
次によくある謡い文句ですが、揉めないと思っていて書類収集などの手続きを省略するリスクを解説します。
3.書類収集等の手続きの省略
遺言がない場合、遺産分割協議を行いその結果を証した遺産分割協議書を作成し、金融機関・法務局などに提出するのですが、その前提として遺産分割協議に全ての相続人が、参加していることを証明するために、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などの書類を収集し提出する必要があります。
戸籍謄本に関しては、本人の転籍・婚姻・離婚そして法の改正などの事由がある度に戸籍は新しく作り直されるため、その戸籍を全て集めるためには、かなりの時間がかかります。
遠方の市区町村に戸籍を請求しなければならない場合もあり、数か月間要する場合もあります。遺言の作成方法によっては、この書類の収集等の手続きも省略できるため、相続人の負担をかなり減らすことができるでしょう。
遺産分割協議の省略
前述のとおりですが、障害者の親なきあと問題の対策については、意思能力の不十分な相続人のために、遺産分割協議を省略できる遺言の作成は必要不可欠となります。
公正証書遺言については、専門家の助言のもと作成すれば①~④の全ての機能をほぼリスクなく利用できるのですが、自筆証書遺言については検討すべきリスクが発生します。
自筆証書遺言の長所・短所
自筆証書遺言の特徴として、要件を満たして作成すれば、自宅で一人で作成することができます。
なお自筆証書遺言の要件は以下のとおりです。ただし、今後の相続法の改正により、緩和される予定がありますので、現時点での制度での要件を記載いたします。
- 全文を自書すること.現時点では、パソコンなどで印刷したものや録音・動画などでは遺言として認められず、直筆のものに限られています。
- 日付の記載.重要かつ抜けてしまいやすい点です。複数の遺言書が存在した場合の遺言の効力は、日付の順によって変わってきますので、日付の記載も要件になっています。なお「平成〇〇年〇〇月吉日」などの正確に特定できない記載方法ですと、無効になってしまいますので、ご注意ください。
- 署名.遺言者自身の名前を署名します。実務上は生年月日や住所なども併記します。
- 押印.拇印などでも効力を生じますが、一般的には実印を押すことが多いでしょう。
自筆証書遺言の最大の長所は
・「手軽」につくることができる
・「安価」でつくることができる
この二つであると考えられます。公正証書遺言作成の場合は、公証人との日程調整や証人の確保などの手間がかかります。公証人手軽料もかかってきますので、作成の負担が大きいと言えるでしょう。この点、自筆証書遺言は、作成そのものには手数料もかからず、自宅で作成でき証人も不要です。
よって自筆証書遺言は、今後環境が変わる可能性が高い高齢者以外の方の遺言に向いています。障害者の親なきあと問題では、比較的年齢層の若い方々でも対策が必要となるため、自筆証書遺言での作成をご提案する場合もあり得ます。
しかし自筆証書遺言には短所がいくつかあります。
その短所について対策をする必要があるのであれば、公正証書遺言で作成すべきでしょう。ここから自筆証書遺言の短所を説明していきます。
1.遺言の成立が正式なものか争いになることがある。
遺言が本当に有効なものかどうか争う裁判例は数多く存在しています。筆跡鑑定や押印の印影によって、ある程度は判断されるものの、当時の意思能力の状況などの判断は非常に難しいです。
「認知症の父をだまして無理やり遺言を書かせたのではないか。」
などというような文句を言う相続人がいると争いになりかねません。
当然、裁判で争うこと自体が不経済なことですので、こういった争いが考えられるようであれば、自筆証書遺言での遺言作成は向いていないでしょう。
公正証書遺言で作成した場合でも、このような争いは絶対に起こり得ないとは言えないのですが、公証人と証人2人の立会のもと作成するので、自筆証書遺言よりは成立に疑義が生じることは少ないと言えるでしょう。
2.遺言そのものを紛失してしまったり、誰かに捨てられたり隠されたりしてしまう可能性がある
自筆証書遺言は作成した後、自身の手で管理をする必要がありますので、自宅のどこかなどに保管する必要があります。あまりにわかりづらいところですと、死後見つからない可能性もありえます。
反面、わかりやすいところに置いてしまい相続人の誰かが見つけてしまった際に、遺言の内容が自身にとって都合の悪い場合に、相続人がその遺言を隠してしまったり、燃やされてしまったりしてしまった例もあります。もちろんその行為自体も、刑法上罰せられる行為でありかつ相続権を失ってしまう行為なのですが、書いた本人が亡くなっている場合はそのまま明るみにならずに遺産分割が進んでしまっていることもあり得るでしょう。
使用する際に作成した本人が亡くなっている遺言の性質から、保管方法には気を遣う必要があります。保管方法の一例としては、財産を受け取る予定の相続人に保管してもらうという方法があります。それであれば、大切に保管してもらえますし、隠されたり処分されたりする可能性も低いでしょう。
この点、公正証書遺言であれば、遺言書の原本を公証役場で保管するため、遺言書の紛失・滅失の恐れはありません。
①、②についてまとめると、やはり相続人同士が不仲、または遺言者と相続人で不仲なものがいて、潜在的に争いになりうる場合は公正証書遺言で作成をするべきでしょう。
3.相続発生後、相続人が諸手続きを行うことが難しい。または早急に相続手続きを進めたい。
自筆証書遺言は、相続の発生後に「検認」という手続きを行う必要があります。検認とは、裁判所において亡くなった時点での遺言書の内容を保存する手続きのことを言います。この検認手続きは、遺産分割協議と同じように遺言者の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等の書類を収集・提出する必要があり、かつ裁判所申し立て書類の作成や裁判所との期日の調整などの打ち合わせもあるため複雑かつ時間のかかる手続きとなっています。
相続後、ゆっくりと手続きを進めていける場合であれば良いのですが、相続人が遺言者の財産に生活を依存している場合などは、この検認手続きがあることで数か月間の間財産を引き出せず困ってしまうことがあります。また、相続人が自身で手続きを進めることができないような場合であれば検認手続きの依頼自体もうまく行かないこともあり得ます。
この点公正証書遺言の場合は、「検認」手続きは不要ですので、すぐに手続きを進めることができます。
まとめると相続人が死後の手続きを行うのが難しい・煩わしいという場合や、家族が遺言者の財産に依存して生活している場合などは、公正証書遺言で作成すると良いでしょう。
ここまでの通り、自筆証書遺言と公正証書遺言。それぞれの長所・短所を理解したうえで作成するべきでしょう。

障害者の親なきあと問題と自筆証書遺言・公正証書遺言の使い分け
この障害者の親なきあと問題においては、子が未成年であるような比較的若いご両親でも対策をする必要が出てきます。若いご両親の場合、これから遺言の内容が変わることも多分にあり得ますので、費用や手間のかかる公正証書遺言は不向きであることが多いです。もちろん、他の相続人との争いが考え得るときなどは公正証書遺言で作成するべき時もありますが、そうでないときは、無理をせずに自筆証書遺言で作成すべきでしょう。
生命保険契約・生命保険信託などを併用すれば、「検認」期間の生活費なども遺言に影響せずに捻出させることもできます。このように自筆証書遺言と他の制度を組み合わせることで十分な対策をとることもできるでしょう。
公正証書遺言作成の流れ
1.文案の作成
公正証書遺言を作成する場合、細かい内容は公証役場にて作成してもらえますが、そもそも誰にどのように遺すべきかという点については自身で考える必要があります。この点については法律家等の専門家に依頼すれば、アドバイスを受けながら作成することができます。
2.必要書類の収集
・印鑑証明書
・ご実印
・相続人との関係がわかる戸籍謄本
・相続人の住民票
・不動産がある場合は登記事項証明書・固定資産評価証明書
などを集める必要があります。専門家に依頼している場合は代わりにこれらの書類を収集してもらえるのですが、自身で用意する場合は、区役所・法務局・市税事務所などをまわって収集しましょう。
3.日程調整
公証人との日程調整をします。公正証書遺言作成には、証人の立会いも必要なので証人の確保もする必要があります。この証人は、相続人とその家族関係者以外のものでなければならないので、なかなか証人の確保が難しいと言われています。この点についても専門家に依頼していれば、専門家に証人としての責務も依頼できますので、日程調整もあわせて専門家に任せることができるでしょう。
4.実際の作成
あらかじめ提出してある文案をもとに、証人の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を後述し、公証人がその内容を確認していきます。その内容に間違いがなければ、遺言者と証人が押印し、遺言者が完成します。
専門家に依頼するかどうかで大きく手続きの負担が変わってくるので、費用と効果を比べて検討すべきでしょう。
遺留分について
遺言を作成する場合に、注意しなければならない点がこの「遺留分」についてです。
一般的な遺留分の意味と、障がい者の親なきあと問題で出てくる特有の遺留分の問題をご紹介します。
「遺留分ってなに?」
遺留分とは、簡単に言うと「遺産のうち、最低限これだけは家族に遺しておくべき」というように民法で定められた権利のことで、相続人の生活を守るための権利と言われています。
例えば、両親と子供の三人の家族で、父親の収入と財産のよって家族全員が生活をしている場合、父親が「全財産を宗教団体へ寄付する」というような遺言を書いたときに、残された母親と子供は生活がままならなくなってしまいます。
そのようにならないように、民法では下記のとおり、遺産に対しての最低限の権利を定めています。
配偶者(夫から見た妻・妻から見た夫)→遺産の4分の1
直系卑属(子や孫)→直系卑属全員合わせて遺産の4分の1
直系尊属(父母・祖父母)→配偶者がいれば、直系尊属全員合わせて遺産の6分の1。いなければ、直系尊属全員合わせて遺産の3分の1
兄弟姉妹が相続人なる場合もありますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分を無視した遺言は書けないの?
よくある質問のひとつです。全財産を〇〇にといった遺言も書くことは可能です。遺留分はあくまで、配偶者や子供に保証するための制度ですので、死後その請求をするかどうかは配偶者や子供たち次第ということになります。
例えば、若いうちに死期が来てしまい、子供がまだ若いうちに亡くなってしまいそうになり、まだ自身で財産を管理することが難しい子供たちの代わりに、全財産を配偶者に相続させるというようにした場合です。基本的には、子供たちが成人したあとについても含めて、子供から親に対して遺留分の請求をすることは珍しいのではないかと思われます。
よほど仲が悪いのであれば別ですが、いずれは親が亡くなったあとにそれらの財産は子供が相続することがほとんどです。わざわざ遺留分の請求をして争うということは珍しいのではないでしょうか。
相続が起こった際に、全財産を配偶者が相続することは、相続税の兼ね合いからもよくある分割方法なので、そこに関して遺留分を請求しようとする当事者は少ないように思えます。ただし、制度上は子から親への遺留分の請求も可能です。こればかりは親子間の関係性も影響するところなので、ケースバイケースと言えるでしょう。絶対に大丈夫ということは言えない部分です。
「仲の悪い相続人がいるので、できるだけ財産を渡さないようにしたい。遺留分を無視することはできないのか。」
これもよくある質問の一つです。
結論から言うと、遺留分を請求させないようにする遺言は難しいと言えるでしょう。遺留分はとても強い権利なので、仮に生前贈与をしていたとしても、亡くなる直前であったり、遺留分を害する前提で行われた贈与である場合は、やはりそれも遺留分の請求の対象になります。
生命保険契約や民事信託を利用すれば遺留分に対抗することができるという見解を持っている方もいますが、判例の中ではっきりと明示されている訳ではないので、当相談室としては前述のように遺留分請求を確実に回避するのは難しいという見解をとります。
ただし、遺留分を見越したうえでの遺言書作成は可能ですので、その例をいくつかご紹介しましょう。
1.争いを避けることを重視し、遺留分の分だけ遺す
遺留分の請求に対して避けられないのであれば、その分を生前に計算し、できるだけ財産の遺したくない相続人にその分だけ遺しておくという手段があります。何の対策にもなっていないと感じるかもしれませんが、これには大きな意味があります。
まず一つは守りたい財産を守ることができるということです。
たとえば、遺産の内訳が先祖代々受け継がれてきた「土地と建物」と、「預貯金」だったとしましょう。相続人は子供二人、長男と次男で、次男は家族全員と仲が悪いといった事例で考えていきましょう。
こういったときに、先祖代々受け継がれてきた土地と建物をどうしても長男に継がせたいというときに、次男の方に遺留分の分だけでも遺言の中で預貯金を遺しておけば、少なくとも土地と建物を長男に遺したとき、次男からその土地と建物に対しての遺留分の請求を受ける可能性を減らすことができます。
また、争いにかかる費用を減らすことができます。金額が納得できないなどの事情があれば別ですが、遺言の中で適正な遺留分をもらえていれば、遺留分に関して争いになることは少ないでしょう。この「遺留分争い」ですが、意外とお金がかかります。
遺留分の請求を行う際は、基本的に弁護士等の専門家に依頼する場合が多いです。この専門家費用についてですが、事務所によって報酬は違うものの、争いになっている遺産額に対して「割合」でかかってくるので、かなりの金額になり得ます。詳しくは適当な弁護士事務所・法律事務所のホームページなどで見てみましょう。
裁判になってしまえば、その割合に対する報酬が、訴える側と訴えられる側でそれぞれかかってきます。そうなると、気が付いたら双方合わせて遺産の半分以上に相当する額が裁判費用に使われてしまっていたというようなことも十分に考えられます。
そもそも遺言の中で遺留分争いにならないようにしておけば、この裁判費用や裁判にかかる費用や時間を節約できるので、大変意味のある対策と言えるでしょう。
遺言とは本来争いにならないように作成するものですので、争いを避けることを重視して遺言をつくるのは、遺言の本来の趣旨にあった対策であるのではないかと考えます。
2.財産を渡したくない相続人に一切の財産を遺さず、財産を受け取る相続人が遺留分の請求できる期間、逃げ切れることを願う
こちらも取り得る対策の一つです。まず「遺留分」を請求する権利は以下のような「時効」が定められています。原則として、こちらの期間の間に請求しなければ遺留分を請求することはできません。
- 遺留分の請求する相続人が、遺言者が亡くなったことを知った時から1年間
- 遺言者が亡くなってから10年間
この期間、遺留分の請求を受けずに時効を主張すれば、遺言はそのまま財産を受け取った相続人のものになります。現在、TV番組などで相続の特集などが増えてきたものの、「遺留分」という言葉の認知度はまだまだ低いのではないかと思われます。遺留分を請求できることを知らないまま、1年が経過してしまうことも十分考えられます。
また、遺言者が亡くなってから10年という期間は、亡くなっていることを知っているかどうかを問わず進行するので、連絡をほとんど取らないような相続人であれば、知らぬ間に期間が経過してしまっていたということもあり得ます。
他にも「付言事項」という遺言の項目の中で、「遺留分の請求はしないでほしい」という旨の言葉を遺すことは可能です。残念ながら法的効力はないものの、人情に訴えかけることはできるでしょう。
いざとなれば請求されたときに相続人たちが考えれば良い、と開き直って遺留分を気にせず遺言をつくるようなパターンもあり得ます。
(1)・(2)と説明しましたが、最終的には遺言者がどうしたいかというところにつきるので、それぞれの状況を整理し、法的な情報をすべて整理したうえで、遺言者自身が判断するということが重要です。
個人的な意見としては、「遺留分争い」になってしまうと、お金だけではなく時間や労力も大きく奪われるので、相続人のことを考えるのであれば、余計な争いが起こらない方向で進めることも愛情のひとつなのではないかと考えます。
障害者の親なきあとに関する特有の遺留分問題
「遺留分」については、一般的な相続でも問題になるところ、相続人になり得る家族の中に知的障害・精神障害を持つ方がいて、意思能力が不十分な場合、気を付けるべき点があります。以下の事例でご説明しましょう。
- 父親(60歳)、母親(60歳)、子供二人の4人家族。
- 長男(35才)が知的障害を持っていて、両親とともに暮らしている。意思能力が不十分でありひとりで生活することや財産を管理することは難しい。
- 次男(30歳)は近くに住んでいて、両親が亡くなったあとは長男の面倒を見ながら生活をしようと思っている。
- 夫婦の財産は父親の名義で管理していて、父親は自分が亡くなったあとの財産を全て次男に相続させ、長男や老いた母親のための財産の管理・利用・処分を全て次男の名義で行えるような遺言を作成しようと考えている。
- この事例の中で、父親の遺言の作成そのものは作成するべきであるということは、前述のとおりです。父親が亡くなった段階で、父親名義の財産は全て凍結されてしまし、遺産分割協議を行わない限り、財産の処分や名義変更などができなくなります。そうなると、遺産分割協議を成立させるために長男のために成年後見人を選任しなければなりません。裁判所で選任された成年後見人も納得する遺産分割協議の内容でなければ手続きが進まないことも難点のひとつですが、長男はその後成年後見人が付いたまま一生を送ることになるので、後見人報酬も総額にするとかなりの金額になります。
そういった状況の中で遺言を作成するのですが、今回父親の考えるとおり次男のみに財産を相続するように作成する場合、懸念すべきは長男の遺留分についてです。
一般論として、意思能力が不十分な障害者に財産を遺しても、自身で使うことができないため無駄になってしまうという考えがあります。その考え自体は間違っているとは言えないのですが、ここでも遺留分への対策が必要になります。
この遺言による相続が起こった場合、長男は次男に対して遺留分を請求する権利を持ちます。長男は意思能力が不十分な状況で、かつ次男が管理する財産で生活をしていくことになるのにかかわらず、遺留分を請求するようなことがあるのかという疑問を持たれるかもしれません。ここでネックになってくるのは「成年後見人」の存在です。
遺言があれば、遺産分割協議を省略できるので成年後見人がつくことはないのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、成年後見人がつくパターンはそれだけではありません。
本人の施設との入居契約の前提で成年後見人の選任を求められることや、本人が裁判で訴えられる、または裁判で訴えなければならないような事件に巻き込まれるなどの状況になったときは、成年後見人を付けざるを得ないこともあり得ます。もちろん本来の成年後見制度の趣旨のとおり、家族の支援を受けながらも、財産管理に限界が来たときも成年後見人の選任をすることもあるでしょう。
上記のような遺言し、次男が全財産を相続したあとに、長男に何らかの事情により成年後見人がついた場合についてです。このときポイントとなるのが、「長男の成年後見人が次男に対して遺留分の請求をする可能性がある」ということです。
通常、家族のひとりが全財産を相続したとしても、相続したものが家族全員の利益のためにその財産を使うのであれば、遺留分の請求などは起こりづらいというように考えます。
ただし、家族誰かにに成年後見人が選任される場合はそういう訳にはいきません。成年後見人は、本人の財産を守ることを第一に考えなければなりません。
今回の事例で言えば、長男の財産を守るために、成年後見人は本人が利用できる制度や請求できる権利があれば、長男の代わりに権利を行使する必要があります。
それは遺留分についても同様であると考えることができます。次男が長男のためにも財産を使っている前提があった場合でも、後見人が遺留分の請求をするべきかどうかについては、後見人自身も難しい判断をすることになりますが、現在の成年後見制度における成年後見人の義務を考えると、次男に対して遺留分の請求をすることもあり得るでしょう。
上記のような遺言を作成する場合は、ここに対して対策をする必要があります。

障害者の親なきあとの後見人による遺留分の請求についての対策
親なきあとの遺留分への対策も、通常の遺留分への対策を応用して対策をしていく必要があります。ただし通常の遺留分への対策と異なる点があるので、注意しましょう。
最も大きな注意点としては、遺言者が亡くなったあとでも、成年後見人が選任されるまでは、次男の遺留分の請求に関する時効が完成しないことです。
民法では「時効の停止」と呼ばれる規定があり、意思能力が不十分な者については成年後見人が選任されてから一定期間の間は事項が完成しないと定められています。よって、相続が起こった当時には何もなくとも、成年後見人が選任された段階で遺留分の問題が生じる場合があり得ます。
つまり時効が適用されない兼ね合いから、逃げ切るということよりもストレートに遺留分を遺してあげる対策をするべきであると考えられます。
今回の事例で言えば、次男に成年後見人がつくまで利用できないことを踏まえたうえで遺留分に相当する金額を遺言で遺すという方法や、生命保険契約・生命保険信託を利用し、次男と保険金の受取人とし、あらかじめ遺留分を請求されたときに備えた金銭を用意することも可能です。
ここまでのとおり、障害者の親なきあと問題については、遺言ひとつとっても奥深い対策が必要となってきます。
障害者の親なきあと問題の対策や、遺言書作成に関してご相談されたい方はこちらへお問い合わせください。










この記事へのコメントはありません。